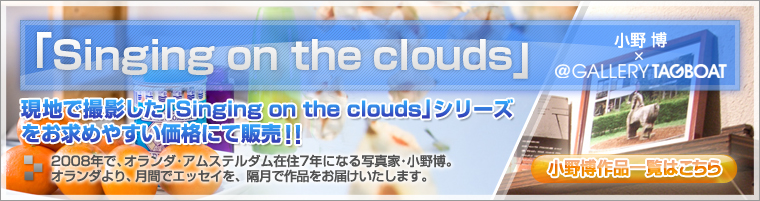アムステルダムはちょうどよいサイズだ。それは街の大きさの話だけれど、まずどこにでも自転車でいけるし、端から端まで横断してもたったの一時間くらいだ。だから公共交通機関に乗らなくてもよい。公共交通機関に乗らなくてよいということは、終電を気にしなくてもよいということである。時間を気にせず、自分ですべて移動できるというのは、気分的にもものすごく開放され、そして街が自分の身体と結びつく。それは地図を見たときに、行き先までの道のりが映像になって自然と頭に浮かび上がるということだ。あそこにあの看板があってそこを曲がると、そうだ劇場のある通りに出てその通りは風が強いと漕ぎにくく、そこを左に曲がると出るあの道は観光客が多いから気をつけないとな。といったように自転車を漕いでいる自分とともにその像が浮かび上がる。そしてアムステルダムという街は具体的な存在になる。

一方の東京は巨大だ。新宿の高層ビルのカフェから眺めたときに都市の終わりが見えなかった。スモッグの向こうにも同じように延々とビルが立ち並んでいる様子は驚くべき光景だ。日本の人口は確実に減り続けているのに、東京の人口は増え続けている。ということは、東京以外のすべての地域から、この目の前に広がる街に人は流入し続けているというこだ。そういえば、ぼくは東京の地図を持ったことがない、そしてこれからもきっと持つことはないだろう。ぼくにとって東京の地図といえば電車の路線図だ。様々に色分けされた路線図を見ながら、どこで乗り換えるかを考えながら目的地の最寄りの駅を目指す。駅に着いたらホームにある地図で目的地を確認し歩きはじめる。目的地まで歩いたこの道が最終的にどこへ行くは知らないし、あまり知りたいとも思わない。だからぼくにとって東京は、いつまでたっても巨大な白い紙の上に点在する複数の駅の群れだ。そして東京はいまでも抽象的な存在のままでありつづけている。
日本に帰国していたある朝、東京で大きな荷物を持って駅で電車を待ってた。いつもは閑散としている各駅停車しか止まらない駅に、ぼくの後ろにはそのとき行列ができていた。後ろに並ぶ人の列を見て、大事なことを思い出した。それはいまが通勤時間であることである。案の定やってきた電車は完全に満員だった。ドアが開いた瞬間、みなぼくの顔を一瞬見て「絶対入ってくるなよ」という目をした。ぼくは荷物を持って、踵を返して改札の方に歩き出し、後ろを振り向くと、さっきまでぼくの後ろにいたたくさんの人達があの満員電車のなかにすっぽりと収まっていた。通勤時間が終わるまで、ぼくは駅前のドーナツ屋でコーヒーを飲んでいた。横の席には学校をさぼった男子高校生ふたりが、向かい合って黙々と携帯メールを打っていた。
2009.2.28