| 2月号 |
 |
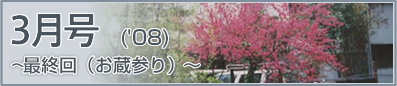 |
| 「’02/03/27」 | ※掲載作品は、画像をクリックすることで購入可能です。 |
僕は人をテーマに写真を撮ることが多いのですが、カメラを構える時、どのように向き合うかはとても重要なポイントです。比喩的な言い方になりますが、構える“角度”を間違えると、永遠に求める場所に辿り着けません。そして僕が最も大切にしているのは<他者性>です。
あたりまえですが、他人は自分に都合よく存在しているわけではありません。どんなに親しくても、さらにはどんなに自分の支配下に置いていると思っても、その人が何を考えているかなんてわかりません。ある日突然、予想もしない行動を取ったとしても仕方のないことです。迷惑だったり、腹立たしかったりするでしょうけれども、受け入れるしかありません。(社会の規範や宗教は、その“予想外”をある一定の範囲内に収めるためにあるのだと思います)
けれども、そんなあたりまえのことが、写真を撮るという現場では大切にされていない気がします。人を写した写真はたくさんありますが、自分のイメージを具現化する道具として使っているものが多い。言葉を代えれば、写している人の思い入ればかりが見えて、被写体となっているその人が見えないのです。極上の刺身にソースをたっぷり染み込ませるようなものです。“作品”と呼ばれる写真には特にその傾向が強い気がします。なぜ対象を“複写”するだけではいけないんだろうと、そういう写真を見るたびに思います。
とはいえ、<他者>を“見る”のは難しいものです。身近になればなるほど、慣れれば慣れるほど、難しくなります。知っているという意識が邪魔をするのです。その結果、目の前にいる人を見ているというより、自分の意識を見ているだけになってしまいます。僕にとっては、こういう慣性から逃れて上手に見ることが、カメラを構えるときの重要なポイントです。
数年前になりますが、この<他者性>を徹底的に追求したらどんな写真になるんだろうと考えたことがありました。そのときに思い描いたイメージがあって、いつか挑戦してみよう、そんなふうに思っていた矢先に、僕の理想を見事に体現している写真家に出会ったのです。蔵真墨(くら・ますみ)です。
街行く人の “見られる”という自意識が薄らいだ一瞬を、「隙あり!」と言わんばかりにストロボ一発、剥ぎ取るように写したモノクロ写真には、ヒリヒリするような“裸の”存在が写っていました。
最近は「蔵のお伊勢参り」というカラーのシリーズに取り組んでいて、伊勢までの道中で出会った人々を写しています。道中といっても、徒歩で本当にお伊勢参りをしているわけではなく、浜松なら浜松に電車で行き、また日を改めて名古屋へというように東京-伊勢間の街々をランダムに訪ねているようです。写っている人も宗教とは全く関係ない普通の人です。本人の言葉を借りれば、「ただ東京を離れたかったのかもしれません」とのこと。
このシリーズでも無意識の一瞬を掠(かす)め撮る技量は健在で、駅のホームに立つ女子高生や道端で何かを待っている中年の男性など、写っている誰も彼もが普通の人のはずなのに(浮浪者などの明らかに際立つ人は注意深く避けているそうです)、異様な存在感があります。「人は誰しも得体が知れない。“普通”などというのはこちらの勝手な思い込みにすぎない」ということを、蔵真墨の写真は改めて教えてくれます。
最近は肖像権の問題がやかましくなり、街でスナップ撮影をすることがどんどん難しくなっています。聞くところによれば、白い目で見られることや罪悪感に耐えられなくなって、写真が撮れなくなるときがあるといいます。やっぱりそうかと、これを聞いたときにすこし安心しました(僕などは撮影プランしか考えていないのに、それでも胃が痛みましたから)。身を切りながら撮っているから“写る”のです。鈍感な人が同じことをやっても、あのように鋭い切れ味にはならないでしょう。
撮られたくないという人がいて、その人たちの気持ちを大切にすることも必要だとは思う一方、こういう写真が発表の機会を奪われてしまうと、予定調和的な都合のいい映像ばかりが蔓延することになりかねません。そのとき消されてしまうのは単に不都合な写真というだけではなく、ある種の現実や存在であり、それに向き合う眼差しです(その眼差しは思想への入り口でもあります)。これはとても危険なことではないでしょうか。
総じて日本の美術家は長年にわたり、それこそ近代以前から、高尚な美を追求するという名目で各自の夢の世界に逃げ込んできました(浮世絵は例外です)。極論すれば、そこには見る人の個人的な好き嫌い以上のものは何もありません。日本の社会で美術が「他人事(ひとごと)」のような扱いを受けているのは、このあたりにも原因があると思います。
社会とのヒリヒリするような関係の中で制作する蔵真墨は実にかっこいい。日本の写真家は、美術家たちが放棄してきた(蔑んできた?)こういう世俗的な部分を担ってきました。僕は、この流れを引き継ぐ人がこれからも次々に現れてくれることを願っています。もちろん、写真家に限らず。
さて、この連載は今回で終わりです。当初の目論見だった「偉大な写真家になれそうな」気持ちになった人がどれだけいたかは疑問ですが、なにはともあれ、長い間おつきあいいただき、ありがとうございました。なお、本連載では敬称を略させていただきました。ご了承ください。
タカのリュウダイ/'08/03/05
※エッセイ中に掲載の作品は全て販売しております。
※作品を良く見たい方は画像をクリック!
| 2月号 |











